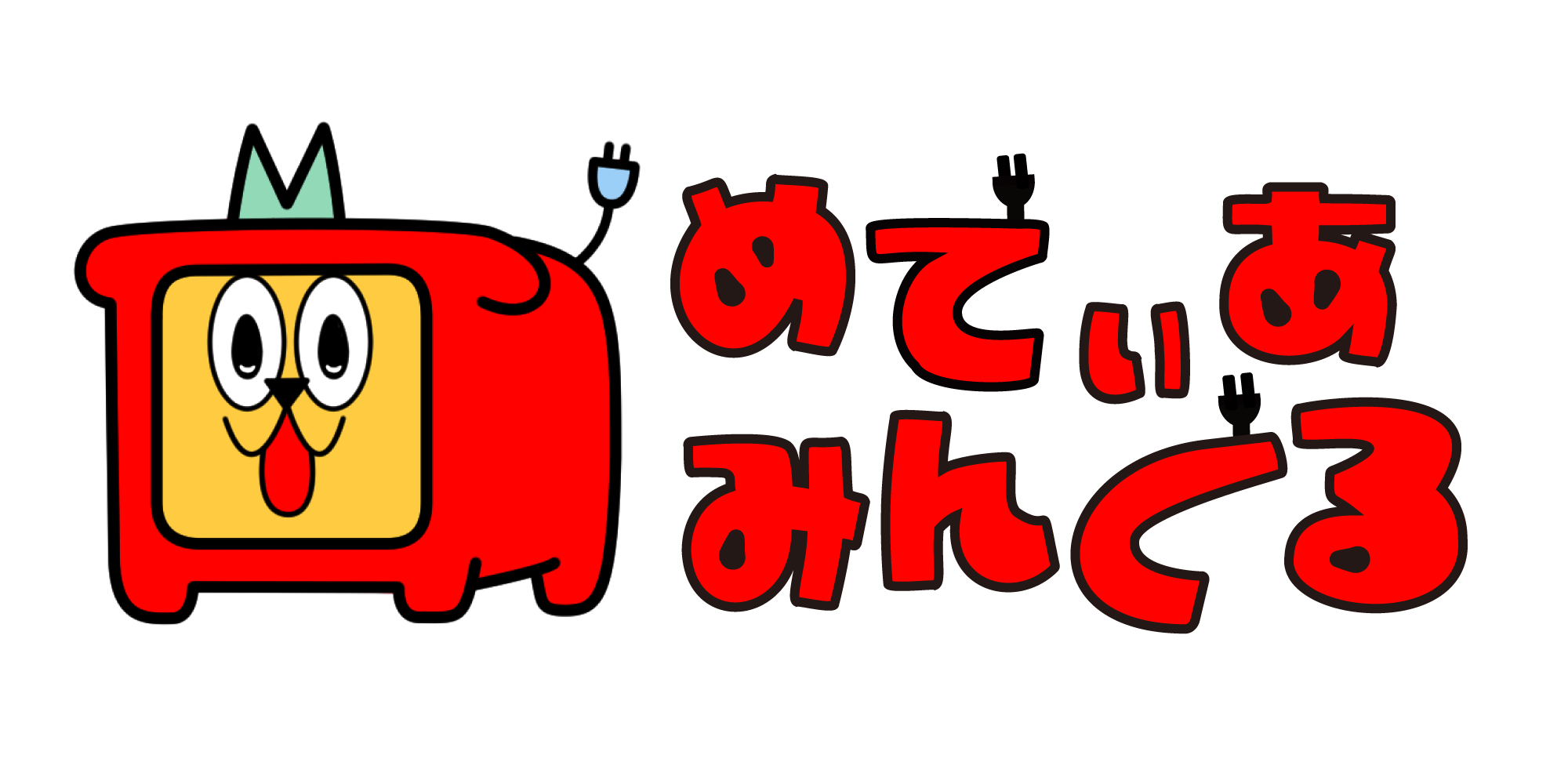いま、「祭り」が危ない!

日本には多種多様の「祭り」が各地で伝承されている。だが、伝統行事としての「祭り」が、各地で存亡の危機に瀕している。
少子高齢社会による伝承者不足。時代の変化による地域のつながりの希薄化。そして、追い打ちをかけるようにコロナ禍が「祭り」の開催機会を奪っていった。
地域の祭りはどのように残していくべきなのか。今回は名古屋市に伝わるひとつの祭りをテーマに祭りのあるべき姿を見ていきたいと思う。
300年続く「戸田祭り」
まずは上記の動画を見ていただきたい。名古屋市の西端に位置する「戸田」地区で行われている「戸田祭り」を名古屋市が密着取材し、名古屋市公式チャンネルで公開されているものだ。
※上記はダイジェスト版である。フルの本編も公開されているので、興味ある方はぜひ本編も併せてご覧いただきたい。
戸田地区は今でこそ住宅地であるが、江戸時代は田園地帯であったという。五穀豊作を祈る行事として今から300年以上も前に始まったのが「戸田祭り」だ。
戸田地区には「割」という名でエリアが区分され、それぞれの「割」が各々で山車を作り、からくり芸や囃子を交えつつ町内を練り歩くお祭りだ。
2002年から5つの山車が一度に集結する「大祭」を、4年に1度開催されるようになった。名古屋市がこの動画を取材した2022年は、その大祭が2日間にわたって行われている。名古屋市指定無形民俗文化財に指定されていることもあり、参加者も多い、大規模なイベントだ。
台風もコロナ禍も越えて
だが、その戸田祭りも存亡を危機を迎えた時期があった。1959年の伊勢湾台風は名古屋に甚大な被害を及ぼし、各割の山車も長期間水に漬かるなどの被害を受け、傷んでしまった。伊勢湾台風の襲来から20年は祭りは途絶え、人々の記憶から消えつつあったのだ。
祭り好きな地元住民がいたことは幸いだっただろう。20年の時を経て祭りは復活し、文化財の指定も追い風となって勢いを取り戻すことができたのだ。
動画では言及されていなかったが、2020年と2021年の開催がなかったのはコロナ禍の影響であることは間違いないだろう。コロナ禍の影響で2023年現在も再開に至れていない祭りも多い中、「大祭」のある2022年に再開できたことは嬉しい話だ。
「地域の絆」を感じつつ
地域の祭りは、その地域がまとまっていないことには成り立たないイベントだろう。戸田祭りには子供から高齢者まで、幅広い層の地域住民が参加している。参加者たちは祭りのための芸や技を前もって習得しなければならず、動画でも祭りに向けての練習風景が取り上げられている。
現代社会ではこういうものを面倒とか嫌だと感じて参加しない人も多い。恥ずかしいことに、これを書いている私自身、子供の頃から地域の祭りを面倒くさいと感じ敬遠してきた面がある。私の地元では地域の祭りに参加しない子供も多かった。
戸田祭りの場合、担い手不足を補う目的で、子ども会を通じて子供たちの参加を促し、その協力を得て成り立っている。それでも、子供たちは嫌々な顔は一切見せず、仲間たちと祭りを楽しむ姿や真剣に芸に取り組む姿などを見せている。
若年層の方が数多く参加しているのも印象的だ。祭りを後世に残していこうというやる気に満ち溢れている。
そこには、戸田地区の「地域の絆」がしっかりと息づいているように感じる。直接じゃなくても繋がれる現代の世の中でも、これだけ多くの地域住民が一堂に集まり、繋がっていく。ある意味理想の姿なのかもしれない。
後世に伝えていくために
締めの「まとめ」の部分です。
祭りは、その地域の昔を知るうえで貴重な史料だ。だからこそ、確実に後世へ伝えていく義務が私たちにあると思う。
なにも、現地で携わる人たちだけが祭りの参加者ではない。動画でもいい、この記事でもいい、祭りの魅力と地域の思いをオンラインで感じ、広く発信していく人たちは皆、祭りの参加者と言っていい。地域の垣根を越えて、世界中の人へ祭り文化が拡がっていってほしい。